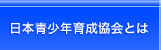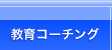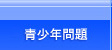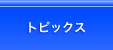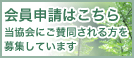2004年度 交換留学生
田代 尚大 君
西部学園文理高校出身(ワシントン州) |
アメリカでの留学を終えて。
自分の中で何が成長したのか、それは最近日本に帰ってきてようやく実感できてきている。留学に出る前、ある人からこんなことを言われた。
「大人になって戻ってこい。」実際そんなことを言われても、大人と自分たちの違いなんかさっぱりわからなかった。年をとるにつれて、外見や考え方ももちろん変わってくるが、やはり成人式を迎えても子供っぽい人もいるし、十分大人に見える人も世の中にたくさんいる。その人の言葉は私の留学に対する意気込みとなり、目標ともなった。
アメリカでそんなことを気にして生活してみると、同じぐらいの年の人たちがすごく大人に見えてしょうがなかった。というのも、彼らの体は一回りも、二回りも日本人より大きく大人びていたかもしれないが、ある彼らと日本人との大きな違いに気づいた。
それは、他人にどのようなことをしてあげられるかだ。
アメリカ人の友達はほとんどの割合で、放課後仕事を持っていた。自分のためではなく、家族や兄弟の為にろくに宿題もせずに朝の2時や3時まで仕事をしている。日本の友達は例え、仕事を持っていてもあくまで自分の趣味や、買い物のためだけであり、けして家族や兄弟の為にははたらかないだろう。それだけアメリカはシリアスな場所であるというのも事実だが。ほかにも、彼らは友達のために車で送って行ったりとても親切なのだ。それでいて、自分のこともしっかりやっている。親の言うことはきちんと聞き、自分の考えをきちんと持っていた。
私が通っていた、A.C.Davis high school は、生徒数2000人の比較的大きな高校だった。初日の登校日の学校の光景はけして忘れないだろう。というのも生徒のほとんどがメキシコからのヒスパニック系アメリカ人だったからだ。校内ではスペイン語が英語以上に飛び交い、英語でさえ聞き取るのに苦労していた自分には、彼らの会話は自分に鳥肌を立たせたのを覚えている。日本の学校で、アメリカは「人種のるつぼ」ということを習い、スペイン語人口はいよいよ英語を上回るなどとも習ったのを覚えていたが、まさか自分が訪れた学校はそんなアメリカを象徴するひとつの学校であるとは思ってもいなかったからだ。
そんな学校生活も日が経つにつれてとても楽しくなり、休日に学校に行かないのが苦になるほどだった。
ベトは、英語のクラスで知り合ったメキシコ人の親友である。彼は5年前にメキシコから不法にアメリカに移民した。そんな話を彼と最初にしたとき、はじめは敬遠しがちだったが、彼を知るにつれてシリアスな生活をもっていることに、同情しはじめた私がいた。彼は12人兄弟の5人目の兄で21歳、高校三年生である。2000年の12月23日に彼らの上5人の兄弟とお父さんが、夜中に車でアメリカの国境をまたいだ。もちろんペーパー(VISA)も持たないで。末っ子だったベトは、アメリカでの新しい生活と、何かあいまいな大きな希望みたいなものをもってアメリカへわたってきた。
メキシコでの生活はとても厳しく、収入はアメリカと比べて、4分の1ほどだったらしい。高校へ通いだしたベトは、英語という壁にぶつかりうまく良い成績が取れないでいた。そんな理由もあってか彼は今年、ようやくめでたく卒業できたのだ。私の知る限り、彼の生活は日本人の僕が想像するのがたやすくないほど、忙しい。学校帰りはりんご工場へ仕事に行き、8時間後学校の宿題を夜明けごろまで必死にやる。
よくみる彼の顔はげっそりしとても21には見えない。しかし、彼はサッカーを心から愛していた。週末になると彼は、私を誘いサッカーをしに近くのグランドへ良く行った。彼はとても自分の生活を楽しんでいるようにみえた、みんなからも見えるだろう。彼の想像を絶する忙しさを知らなくても。そんな彼は私を変えていった。メキシコ人に対するステレオタイプは消えて行き、学校のメキシコ人とはすごく息が合うようになっていった。ベトとはサッカー部で共に良きチームメイトとして時を過ごした。
You see soccer is the only sport that I play, but because of my grades I was not able to participate. This was hard on me so I told my self that this would not happen again. At the same time my mother told me to remember that the reason that we came to the USA was to have a better life so I need it work hard at school. With my mother and teachers help I have made big changes in my life and schoolwork.
これは、ベトがサッカー協会の規定の年を越えてサッカーをするために、サッカー協会から許可を得るための彼の書いた手紙のひと部分だ。この文からもわかるように彼の生活の大変さが身にしみた。
ステレオタイプという言葉を知ったときに全身に何か駆け巡るのがわかった。
アメリカでの英語の授業で習ったその言葉は、その頃の私にもっとも身近なものであったからだ。私のステレオタイプによって、私はメキシコ人を敬遠しがちにいた。彼らの生活習慣やすべてを異常なもののような見方をしていた自分をすごく恥ずかしく思った。
ベトの家に遊びに行ったとき、彼の家には独特のメキシコ人の匂いが充満していた。あの独特のタコスの匂いだ。ほかのメキシコ人の友達の家に遊びに行っても同じような匂いがやはりした。ヨーロッパ系のアメリカ人の家にいってもまた、メキシコ人とは違うような匂いがすることに気づいた。匂いというものはそれぞれの文化や生活習慣に関係していると思った。
そんなお互いの文化を知らない状態からステレオタイプは、テレビや新聞のニュースとして、さまざまな真実とは異なった情報として作られていく。そういう情報操作によって作られた僕のステレオタイプは、好ましいものでなかった。そして、世界中の人々もやはり、そのようなステレオタイプを個々に持っているだろう。友達に、日本人のステレオ的な印象を聞いてみると、背が低いや、顔の表情があまり無いや、頭がいい、いつでも刀をもっている。などだった。どのようにしてそのような、情報が作られ耳に入ったのか。私はとても不思議に思った。日本人はどうせ〜だから。とか日本人をしらない身で言われてほしくない。そしてアメリカ人だけでなく、世界中の人にも言われたくないし、お互いステレオタイプによって言い合うのもいやだと思った。そして、自分がどのようにそのようなステレオタイプをこの先、将来のなかで変えられるのか考えた。わかってきたのはやはり自分で地域それぞれの文化を知ってそれを多くの人に伝えることだ。アメリカだけでなく、アジアの中でも台湾も中国も人それぞれ文化や生活習慣も異なるだろう。そういう色々な人の文化の背景や生活習慣をこれから学んでいき、たくさんの人に伝え、差別や偏見の無い平和な世界を作るための少しでも力になりたいと思っている。
留学を終えて、自分に点数をつけるとしたら95点を迷わずつけるだろう。けして、自分に甘いわけではない。自分の辛かったことをきちんと知り、何よりも、目標以上のことをしっかりやり遂げられたことがこの得点に結びついている。
さまざまな経験を通して、これからは英語の授業で習ったステレオタイプを変えていける人間になること。
そして、この留学を通して色々なことを学びみてきたが、この交換留学でお世話になったJYDAの春の文化学習講座の授業の中でこんな話しを聞いた。
「目の見えない人達が象をなでた。ある人は、象とは細長くてくねくねまがる。また、ある人は薄っぺらくてひらひらしている。みんなそれぞれ正しいが、ほんとの象は知らない」この話は、私の経験を今後どのように生かすかを、示しているかのように思えた。
いくら自分がアメリカはどんなとこだよ、と自分の経験からそんなことを言っても、それはアメリカという国のほんの一部、ほんの少しの人間を知れただけで、けしてアメリカすべての本当ではないこと。
日本人の私でも日本のすべてを的確に知っているわけでもないが、アメリカと日本を同時に見比べさらに多くのことを知っていきたい。今回の留学を無事に成立させていただいた先生方、またアメリカの家族、日本の家族、JYDAの人達に心から感謝したい。 |
2004年度 交換留学生
田代 尚大 (母) |
YOU RAISE ME UP
息子が生まれ18年間、私達はいろいろな経験をする機会を息子に贈ってきています。あらゆる体験を通し、そこから生まれる何かを掴み取って、尚大にしか出来ない生き方を自分自身で、見つけてもらう事、望んでいました。帰国し今、改めて、「かわいい子には、旅をさせよ」の親の心境が、痛いほど解り、まさに私の気持ちに反映しているのではないかと思います。目の届くところにいると私の愛情、また尚大が親に感謝を抱くことなど思ってもいませんでした。長い旅に出て距離をもったからこそ、お互いの新たな発見ができるようになり、ストレートにありのままの姿で感情も愛情も素直に伝わるようになりました。そして、彼が見て感じたアメリカの話しを冷静に受け止め、長かった旅の終わりを感じています。彼にしか出来ないアメリカの生活は、誇らしく自慢できる経験となりました。
あれほど待ち望んでいた息子の帰国から3ヶ月以上の月日が過ぎようとしています。すべての面で成長した息子の存在は、新鮮で羨ましくもあり、眩しくも感じられます。留学以前の彼は、毎日時間との戦いで、学校、予備校生活の忙しい日々を送っていました。ただ単に目の前にある漠然とした良い成績取得の為だけに生活していたように思います。時には、逃げ腰になり現実から、目を反らせたいこともあったでしょう。でも、何も言わず生活をしていました。私からみても将来の夢を持つなど考える余裕などないことは、分かっていました。そして、日本のこの環境では自分自身変えることが難しいことも。私は、もっと伸び伸び、活き活き生活を楽しんでもらい、自分の人生を大事にし、冷静に前向きな至誠を持ってもらいたいと思っていました。私も彼と同じくらいの年の頃、アメリカ留学も真剣に考えていました。でも、あの頃には今のような留学の手段もなく、諦めてしまった自分を思い出し、それなら、アメリカンスクールに入り、英語を勉強したいとも思いましたが、親が英語で話せないと入学は無理との事でした。あの頃を振り返ると英語の勉強より何かを自分で変えて行く機会を求めていたのかなと感じます。その諦めは、今、まだ心に残っています、それは、実現できなかったからです。そして、尚大の強い希望の、絶対2度と経験できない公立高校交換留学の夢は、問題なく実現されました。私は自分の事のよう賛成しました。現実に留学が決まり、地図にも載っていない田舎の町ワシントン州、シーラで9ヶ月過ごすことが出来ました。そこでのかけがえのない経験が彼の成長を見事に促していました。
帰国後すぐ、日本の高校へ提出するレポートは、私を驚かせました。と言うのは、留学中何も愚痴をこぼさず、悩みも知らされず順調な生活を送っていると思っていた私でしたが、レポートの冒頭で「自分の中で何が成長したか?」と書かれてあり、興味をそそわれ一気に読みました。涙ウルウルどころか、泣けました。彼のアメリカ生活の苦労、感じたこと、すべて知ることができ、感動しました。それは、彼の体験の一つにすぎないが、アメリカの留学なのに彼が通った学校の生徒殆どが英語ではなく、スペイン語を話すメキシコ人が多かった事。英語さえ満足に話せなかった彼にとって9月の登校日は、まさにショックの一言だったでしょう。確か私宛のメールに一言、「白人居なくびっくりした!」と書いてありましたが私は気にも留めていませんでしたが、その後、彼は、自分の葛藤もあったでしょうが、自分を変えられ、メキシコ人のベトが親友となり、ステレオタイプの考えをもっていた自分に気ずき、だんだんと打ち解けていったというレポートでした。彼の9ヶ月間の留学中の心の変化が解り、とても頑張って生活していたのだと、このレポートで多くの彼の成長の理由、知ることが、できました。
また、甘える人がいない生活で、今まで気が付かなかった暖かい人とのふれ合い、社会のルールの大事さ、家族への感謝の気持ち、豊かな自然のありがたさなど、たくさんのことを、肌で、心で感じてきました。その経験から、以前とはどこか違う息子になり、自分らしさを持ち、正面から立ち向かう勇気も備わってきたのでしょう。
彼から送られてきたクリスマスカードの言葉「Thank you for my good experience........Thank you for everything」このあたりまえの、この一言にも胸が熱くなりました。
そして、息子を家族と同様に長い期間預かってして頂いた、ホストフアミリーとの対面は、決して忘れられない思い出となることでしょう。我息子は、家族に対し自然体で、リラックスしていて、日本の生活とは違い、恥ずかしながら嫉妬すら感じました。アメリカの家の家族メンバーは、5人兄弟と犬2匹、おまけに外には、hot tubもあり、蛇も飼っていました。兄弟の上2人は、少し離れた大学に通っていて、家に住んでいませんでしたが、一人っ子の息子にとっては、あの家族でワイワイする会話、環境すべて、適していました。この環境も最高でした。納得です。ホストであるMam、Dadは、息子の意見でさえ一人前に尊重する態度、明るく、バイタリティがありスポーツ好き、開放的な家で人種など関係なく開かれるパーティも多かったようです。訪れた私たちに対しても自然体で接し天真爛漫の会話、楽しいひと時でした。ホストの話で、多くを学び、私の今の生活にも、プラス思考の影響をもたらしています。また、訪れたアメリカでの2倍の感激は、映画の一場面を大きなスクリーンで見たかのような息子のアメリカの高校の卒業式に招待され参加できたことです。9ヶ月足らずの留学で卒業式に参加できたことは、予想外でした。そして、卒業式のイベントには生徒のすべての家族、親戚が参加し、全員で喜んで楽しんでいる姿は、私にも伝わり深い感動を受けました。どの国に暮らしていても、家族の子供の愛情は強く、同じだということも。そして、イベントの最後で卒業生の独唱の歌が、最高でした。絶対胸に残る歌となるでしょう、涙がでました。Josh Groba、「You Raise Me up」の歌です。息子の留学生活、息子を思う私の思い、すべてこの歌で、気持ちが通じあえた気がします。10ヶ月の生活はこの歌に託されているでしょう。
書きたいこと、私の気持ち、いろいろな事、たくさんありますが、JAYDとの出会いがあってからこそまたとない経験で、尚大も大きな夢が見つけられるようになり、今、前進しています。10ヶ月間学んだこの留学経験は、尚大の人生を変えるものでした。私たち家族も影響され、確かな向上をしています。息子の新風は、私には心地よく素直に受けとめられ、新鮮な空気そのものです。尚大の留学は、とても勉強になり、年を重ねた私でもこれから多々勉強する勇気を学びました。今、息子は、将来の夢に向かい新たな挑戦が始まっています。夢が、実現できるよう、親としてはただ、祈るばかりです。でも、きっとすぐに「アメリカの家にちょっと帰るね」と言い残し、日本を後にすることでしょう。もう心配することは、ありません。あの屈託のない笑顔と相手を思いやるゆとりが出来た今は息子を信じるだけです。自信を持って言えます。「いってらっしゃい」と。
最後に、なによりも、尚大と接してくださったすべての方々感謝しております。これからの長い人生、なにが起こるか、計り知れませんが、きっと彼のこの経験は、彼の大きな進歩であり、将来何かの役に立つことを望んでいます。息子は、アメリカの比較的、貧困な学校に通ってからこそ、人の痛みも感じることが、できました。日本にいたらできない経験です。
きっと、この経験を生かし、これからの道、ステレオタイプを無くす世界を少しでも変えていこうとしている彼の願い、私も同様です。これから、尚大の進む道、何があろうと信頼し、陰ながら応援していくつもりでおります。
この機会を与えてくださったJYDAの皆様ほんとうに、ありがとうございました。
この経験は、息子より、私のほうが影響されています、後悔のない生涯お互いに、送れたら良いですね。そう願っています。Good Luck!!
|
2003年度交換留学生
前田 香弥 さん
大阪府 市立工芸高校出身 (コネチカット州) |
私を築くもの
「あなた、何か喋り方が変わったね。前よりもずっと落ち着いて、優しい感じやわ。」いつだったかは忘れたが、久しぶりにアメリカから日本の家に電話した時の、母の言葉がこれだった。
2003年7月に私は日本を発ち、一年間を米国東海岸に位置するコネチカット州で過ごした。留学を決意した「英語力の向上」という表向きの理由の裏側には、実は当時感じていた、私を取り巻く閉塞感のようなものから逃れたかったという思いもあった。「日本を出よう。知らない世界に行ってみよう。そうすればきっと何かが変わるはずだ。」この、何とも単純な決意。しかし私の両親は、あっさりと「あなたがやりたいのなら、やってみなさい。」とい言って送り出してくれた。そんな気の抜けたような考えと共に私の留学生活は幕を開けた訳だが、始まってみれば、予想もしなかったような苦難が待っていた。
まずは、言葉の壁という苦難である。言いたいことがうまく伝わらないもどかしさ。些細な間違いから生じる誤解、故に生じる孤独感。とにかく何をするにもこの問題が私について回った。最初の頃は、どうせ言葉が分からないのだからと、よく卑屈な態度になっていた。ゼロから始めて、たったの一年でこれだけ英語が話せるようになったのだから立派なもの、とよく周りに励まされた。それは確かにそうかもしれないが、やはり自分の中では言葉の壁に対しては大きな葛藤があった。そしてこれは結局帰国する直前まで続いた。
次にあげられる苦難は、自国についても他国についても、まるで無知であったことを思い知らされたことである。私がアメリカで通っていた高校は、全校生徒約360人というとても小さな学校で、日本人は私一人、その他のアジア人でさえもほとんどいないという環境だった。となると、周りは好奇心から日本のことを色々と私に訊きにくる。それは私にとっても友達を作る為の絶好のチャンスになるはず。しかし、日本の学校や流行っていることについてなら私も答えられるのだが、日本の歴史や政治的な話題に及ぶと、言葉の壁以上に私の知識が追いつかない。仕方なしに、「知らない」と答えようものなら、彼らは自分の国のことも分からないのか、と呆れる訳である。何とも恥ずかしかった。これには参って、帰国したら絶対に日本について勉強し直そう、と心に決めた。
もう一つの苦難は人間関係であろうか。もともと他人であるホストファミリーと人間関係を築いていく過程で、多くの苦労を経験した。そして日本で当たり前の存在だった家族のありがたさを痛感した。幸い、私の暮らした家には私と同い年の女の子がおり、彼女は、英語が全く分からなかった何とも手間のかかった私を、事ある度に親身になって助けてくれ、いつも私を励まし笑わせてくれた。実は私はホストマザーとの仲がそれほど良くなくて、そのことで何度も悩んだり落ち込んだりしたのだが、それでも私が諦めることなく、何とかあの家でやってこれたのは、ホストシスターのお陰である。
もちろん、お互いの性格や意見の相違から喧嘩になったことも数え切れないくらいあったが、今ではすべてがいい思い出だ。つならない冗談で大笑いしたこと、好きなミュージシャンのことで大討論してしばらく口を利かなかったこと、私の”really”の発音がおかしいと言って徹底的に指導されたこと、クリスマスや誕生日のプレゼントをどうするかで必死に悩んだこと、真面目に世界情勢について語り合ってみたこと・・・本当に泣き笑いを共にしてきた。彼女、Lethaはアメリカでできた最高の姉であり大親友だ。
学校での人間関係については、日本にいた時とそれほど変わらなかったと思う。私の友達に関する持論は量より質だということで、アメリカでも少数だが親しくする友達ができた。最初は言葉の壁のせいで、本当にこの人たちは私のことを受け入れてくれているのかな、という不安を覚えることもあったが、それは時間が経てば薄れていった。私が帰国する直前に彼らが心づくしのお別れパーティーを開いてくれた時には、心から感動した。アメリカでできた友達から学んだことは、彼らは皆しっかりとした考えを持っていることだ。日本の学生の方がもっと必死に勉強して忙しくしているはずなのに、どうしてこの人たちの方がこんなにもしっかりとした考えを持っているのだろう、もっと言えば、こんなに遊んでいて、のんきに見えるのに、どうしてこんなにも将来のビジョンをはっきり持っているのだろう、と彼らを見ていて思ったものだ。物事を深く考察し、それに対する自分の考えや意見を具体的に持たなければ、いくら博識であったとしても意味がないことを彼らから学んだ。口に出して自分の考えを他人に伝えることで、初めて自分の存在価値を認めてもらえるということをアメリカで一年暮らす間に痛感した。
一年間のアメリカでの留学生活を通して多くの困難や苦労を経験し、私の従来持っていた価値観がどんどん変わっていった。日本にいた時には感じなかったことや考えもしなかったことを感じ考える多くの機会に触れたことにより、冒頭の母の言葉に至ったのであろうと思う。自分では様々な困難に立ち向かったことによって自信がついたと思っていたが、それが「落ち着いた」と母には感じ取れたのだろう。そして「優しくなった」と母が表現した部分については、日本にいた頃の私は、嫌なこと苦しいことをいつも避けてきたため、傷ついたり怖い思いをしたりすることがあまりなかったのだが、アメリカで初めてそういう経験をし、ようやく周りのことにも目を向け考えられるようになり、一人では生きられないこと自分は多くの人に支えられているのだということを実感し、その結果思いやりを持てるようになったのだと自分では思っている。
留学中は重度のホームシックにはならなかったものの、日本の家族からの励ましがなければ、私は一年間留学生活を続けられなかったと思う。あんなに素っ気無く私を送り出した父が、ある時、「右も左も言葉も分からない場所で、お前がそんなにも頑張っていることを、とても誇りに思う。」と言ってくれたことがあった。精神的にも少し辛かった当時、泣きそうな思いで聞いたあの言葉の重みをこれからもずっと忘れることはないだろう。
これは今だから言えることだが、一年間の留学だけで劇的な人間的成長を期待しない方がいいと思う。一年間の経験が、自分を見つめ直しこれから自分はどうしていくべきなのかを考えるきっかけになれば、それで十分だと自分では思っている。一年間の留学を終えた今、これは終わりではなく新たな始まり、といった感じだろうか。何はともあれ、この留学経験は私にたくさんの思い出を残してくれた。今は前よりも少しだけ自立心と自信がつき、胸を張って生きている。
|
2003 年度生 前田 香弥 (母)
前田 朱美 さん |
ふたつの家族
今回のアメリカ留学で、娘と私の手紙のやり取りは合わせて250通ほどになりました。娘がお世話になっていたコネチカット州に私からのエアメールが届くのに約5日、娘からの返事が私の手元に届くのに約5日。約10日ほどして返事が届いた頃には、先の手紙に自分が一体何を書いていたのか忘れてしまうほどでした。このスピード時代に!と言われるかもしれませんが、私たちは敢えて電話やメールを極力避けて、手紙で近況を報告し合い、娘の泣き言に対して叱咤激励しました。娘がホームシックにかかった時などは、すぐに声を聞くよりも冷静になれ、あれこれ思い戸惑う私も精神的に強くなり、お互いによかったと思います。
「何事にもガマン!ガマン!」「いつも謙虚な気持ちを忘れず!」と何度手紙に書いたことでしょう。娘からの何通目かの手紙に、「ひとり暮らしにずっと憧れていたけれど、ひとりで生活はできても、ひとりで生きていくのは精神的にかなり難しいって分かった。」ということが書いてあったのを読んで、とても感動しうれしかったのを覚えています。これぞ娘を留学させて甲斐があったというもの。
コネチカット州でお世話になった家族、日本で待っている家族、自分にとってこの二つの家族の違い、接し方、想いに色々と戸惑っていたようでした。日本に居た頃は、自分のことを心配し世話を焼き、愛してくれる家族を当たり前のように、時には“うざったく”感じていたであろう娘。たった一人アメリカの地で、違う家族の一員として生活してみて、日本の家族がどれほど自分にとってかけがえのない存在であったか、身にしみて分かったようです。私が娘に望んでいた経験はまさにこれだったのです。英語がペラペラしゃべれるようになるよりも、日本での生活で失われてしまいがちな感謝や尊敬、思いやり、優しい気持ちをしっかり蘇らせてきて欲しかったのです。 娘をお世話してくださったホストファミリーには感謝の気持ちでいっぱいです。これからの娘の人生には、まだまだ色々な困難が待ち受けているでしょう。しかし、あのアメリカでの1年間の経験が娘を助けてくれると信じています。
|
2002年度交換留学生
山口 修平 君
奈良県 一条高等学校出身 (ノースカロライナ州) |
修行留学体験記
僕はアメリカ留学の一年間を終え、日本にいては気づかなかった事を気づかせてもらいました。そして自分にとっての「価値観」「世界観」が劇的に変わったことも一年を終えてから分かりました。 留学先はノースキャロライナ州というアメリカ東海岸の州です。気候に関しては、夏は日本より若干暑めで、冬はつららができるほどの寒さでした。派遣先に移動する前にホストファミリーの詳細が分からず、一人暮らしのジムさんという情報だけで不安もありましたが、空港でジムの笑顔を見ると不安はどこかへ飛んでいきました。ジムはもともとアフリカのガーナからアメリカに移民してきたAfrican Americanです。独り者のジムの家には、アトゥーとリチャードそして後から一緒に暮し始めたケテチエとエスタがいました。家の中は毎日賑やかでした。僕は日本語とつたない英語が会話の手段でしたが、彼らは彼らの母国語と英語というのがそれでした。初めの頃、僕と話している時は英語による会話でしたが、彼ら同士で彼らの母国語で話している時、やはりこちらからは会話に入れませんでした。ある日僕がそのことについてジムに相談すると、「お前は日本人、俺はガーナ人、母国語が違うのは当たり前だけど、英語という共通語があるだろ。お前が英語で話し始めたら俺達もそれに答えるぜ。」という言葉をかけてくれました。その日から僕は、自信を持って英語で会話するようになりました。学校はPage High Schoolという生徒2000人が通う高校でした。初めは各教科の教室の場所も分からないし、助けてくれる友達もいなく、ずいぶん戸惑ったのを覚えています。授業も日本と異なり、討論のような形式のものが多かったので、これにも戸惑いました。しかし少しずつ日を重ねるごとに、自分から意見を発言したり、迷うことなく教室の場所が分かるようになったり、友達もどんどん増えていったりして、学校生活は楽しく充実したものになっていきました。
一年間もアメリカで暮してみると、ただただ憧れていたアメリカという国の良い面も悪い面も見えてきました。それによって今度は自国の良い面悪い面も見えてきました。これは外に出て初めて気づいたことです。日本の家族からそして日本という国から外に出たことにより、自分を見つめ直したり日本の家族に感謝したりするすばらしい機会になりました。これは英語力向上以上に一年間の大きな収穫だったと思います。 こんなすばらしい一年を経験できたのは、「行ってこい」と送り出してくれた両親、どこの誰だか分からない“修平”という人間を一年間も無償で受け入れてくれたジムをはじめ、様々な人々の支えなくしては実現しなかったことです。本当に感謝しています。来年ジムが日本に遊びにくると言っています。ジムにも日本の良い所悪い所の両方を感じてもらえたらいいなと思っています。
|
| 2002 年度生 山口 修平(父)
山口 正幸 さん |
留学した息子を見て
息子は男二人兄弟の長男で、皆に大事に特に祖父母には大変可愛がられて育ってきました。おばあちゃん子で、いつも祖母と行動を共にしてきたので、同年代の子供と比べると、弱々しく頼りなげに感じておりました。それは小学生、中学生と成長していく過程でも変わらず、人の影響を受けやすく、自立心のない様に見えておりました。しかし、中学生の頃よりテニスを始め、スポーツをするようになってからは、体力的には逞しくなり少しは安心していたのですが、まだまだ精神的には弱さがありました。 小さい頃より近所の教会のボランティアで英会話を教えていただいていましたので、いつしか英語に興味を持つようになり、高校は外国語科のある学校に決め、その高校で外国人教師の方々や他国からの留学生と知り合い、また、学校行事で韓国でのホームステイという機会にも恵まれ、ますます自分も留学してみたいと考えるようになったようです。その頃、日本青少年育成協会の交換留学制度を知り、なんとか選考試験をパスさせて頂き、その夢を実現させることになったのです。最初の研修地ミネソタでの3週間の生活は、ホストファミリーの方にご親切に色々な事を教えて頂き、本人なりに楽しくアメリカでの生活をエンジョイしていたようです。3週間の研修を終え、飛行機で一年間の受け入れ先ノースキャロライナ州のグリーンスボロへ着いた時、出迎えてくださったホストファミリーの方が黒人と知り、その時は正直、動揺したそうでしたが、一人での移動で不安はピークに達していて、無事にホストに会え、ホストの笑顔でそんな動揺はふっとんだそうです。ホストの方はガーナ出身で、家にはガーナ出身の男性が何人か同居していたそうです。親としては初めは、どこか心配であったことは事実です。そこでの生活は合宿のような感じで、自分の事は自分でする、食事、洗濯、掃除など日本での生活とは一変し、息子は初めて今まで自分がどれだけ甘かったという事を思い知ったようです。ホストの方たちは皆、真面目でよく働き、国の家族に仕送りし、常々、「俺は必ず成功する。お前もよく勉強して、ビッグになれ、ビッグになれ!」と言ってくれたそうです。息子に、生き方や逞しさ、優しさ、人々に奉仕する精神等々、日本では感じられなかった事をたくさん教えてくださいました。決して自分たちの生活も豊かとはいえないのに、こうして無償で留学生を快く受け入れてくださったその精神には頭が下がります。一時でも不安を抱いた私たちは恥ずかしい限りです。息子のアメリカでの学校生活は、最初の頃は自分をうまく表現できず、色々と苦労したようです。でもたくさんの友達ができるにつれ、すばらしいブレーンにもめぐり会え、助けてもらったようです。何よりも自立心と自信がつき、将来に対しての自分のしっかりした考えを持つようになり、日本での5年、いや10年もっと・・・圧縮したような1年であったと思います。息子の逞しさを見るにつけ、米国でのホストファミリーの方々、学校の先生、友達には言い尽くせないほどの感謝の気持ちでいっぱいです。
帰国してからは逆カルチャーショックもあったようですが、本人の人生にとって、価値観・人生観まで変えて頂いた米国のよき所、また日本のよき所をおりまぜて、これから先の息子に人生に役立てていってくれる事を望みます。
先日グリーンスボロでの友達が日本に短期留学に来ているからと我が家に寄ってくれました。数日間ではありましたが、息子達は再会を喜び、家族で楽しい時を過ごしました。私達まで刺激的な機会を持つことができたのは、息子の留学のお陰です。こんな貴重な体験を親子共々させていただき、いつも見守って下さっていた日本青少年育成協会の方々には感謝の念でいっぱいです。本当にありがとうございました。
|
98年度交換留学生
山本 大貴 君
京都府 花園高等学校出身 (ウィスコンシン州) |
アメリカで「体験」したこと
全く未知の世界であったアメリカという国へ1年間という短い期間ではあったけれども、米国政府公認の交換留学生として赴くことができたことは、僕の人生にとって大きなターニングポイントとなりました。
アメリカは、肌の色や文化的背景の異なる様々な人たちが世界中から集まってできた国です。様々な人種が共存しているからこそ、また独自の文化を形成しているのです。
アメリカ人は、日本人と比べて自分をアピールすると言われます。そんな環境の中で友達をつくるには、僕もやはり自分の個性をアピールしなければなりませんでした。留学先の公立高校でも、僕は外国人という立場であったけれども、まわりの先生や生徒達は、僕を「日本人留学生」としてではなく、「Daiki」というひとりの人間として接してくれました。留学生だからといって特別扱いはされなかった分、逆に言えば、学校でも家庭のなかでも、自分から積極的に自己アピールしなければなりませんでした。もちろん、留学当初は、英語も上手く話せなかったためにいろいろと苦労しました。どうすれば自分を理解してもらえるか試行錯誤の繰り返しでした。そんななかで、僕は自分の得意な空手を通して自分と日本の文化をアピールすることにしました。空手の基本と型を身振り手振りで教えてあげることで、次第に自分の居場所を見出すことができました。言葉の壁が序々に低くなるにつれて、僕は日本の歴史や文化、習慣や学校のシステムのことなど、いろいろなことを紹介しようと努めました。その時感じたことは、いかに自分が自国日本のことについて知らなかったかということでした。時には、日本通のアメリカ人に「あなたは本当に日本人ですか?」と問われたこともありました。こうして僕は、生まれて初めて日本についてもっと知りたいと感じ、そして異なった角度から日本を見つめなおすという機会に恵まれたのです。
アメリカでの留学生活を通して学んだことは、「個性の尊重」、「自国日本の再発見」の他にも数え切れません。ここで、あえてもうひとつ挙げるとしたら、「感謝する気持ち」です。この交換留学プログラムでは、ホストファミリーはボランティアで学生を1年間受け入れてくれます。僕のホストファミリーも、僕を家族の一員として接してくれました。そんななかで、僕はホストファミリーに対する感謝の気持ちはもちろんのことですが、それに加えて日本の家族に対する感謝の気持ちが湧いてきました。日本にいるときは、友人との約束を優先して、家族と一緒の行事に背を向けがちだった僕ですが、親元をはなれて生活することで、初めて、これまでの自分の生活も実は両親の陰からの応援によって支えられていたのだと実感しました。また、苦しいとき、辛いとき、何かに悩んでいるときに常に傍にいて相談にのってくれたのは、自分の家族であり、友人であったことに気づきました。
そういった周囲の人たちに支えられての1年間でしたが、本当に多くのことを学び、精神的にも成長できたと思います。ただ教科書から丸暗記した知識ではなく、自ら体験して培った知識は決して消えることなく、これからの糧となることでしょう。
|
98年度生 山本 大貴(母)
山本 満美子 さん |
留学して変わったこと
1999年7月、1年間のアメリカ留学を終えて我が息子が帰国してから、早くも3ヶ月が過ぎようとしています。心配するほどの逆カルチャーショックもなく、すぐに元の生活に戻り、次の目標に向って頑張っているところです。
息子の口から留学の話しが出るまでの彼の生活振りは、周囲の心配もよそに、自由奔放で決して自慢できるものではありませんでした。高校に入学してからの彼の生活は、特にこれといった目標もなく、部活も2週間程で辞めてしまい、悪にはなり切れないけれど毎日がだるい、むかつく、面白くないと言いながらのだらだらとしたものでした。何かに一生懸命取り組むでもなく、ただ時間を持て余しているようにも見えました。
そんな高校1年生の秋、ふと学校で1枚のハガキを手にしたことから彼の生活は一変しました。ハガキから日本青少年育成協会という団体を見つけ、交換留学プログラを知り、留学説明会への参加、選考試験とトントン拍子で進んでいきました。そして、文化学習講座などの集まりを通して、同じ目的を持つ人たちとの交流が始まり、彼のなかで眠っていた何かを目覚めさせてくれました。「留学」というチャンスを与えていただいたことで、彼の生活も180度変わりました。勉強にも力をいれるようになり、言動も考えてするようになりました。もちろん、「留学」という夢がかなう喜びと共に、ことがあまりにも上手く運ぶので、親子共々、「本当に行くんだね」「夢じゃないんだね」と落ち着かず、不安が拭い去れませんでした。他の留学生の中には、ちょっと海外旅行にでも行くかのようにはしゃいでいたり平然としている姿も見かけましたが、息子に関しては、単身親元を離れるのは国内外で初めて、生活習慣や文化の異なる異国へ行くことの不安と期待が複雑に入り混じり、極度の緊張が家族にまで伝わってきました。
今、思い返してみると不思議なものですが、このような状態で我が息子を送り出したことがつい先日のようです。留学中、痩せるどころか6kgも体重が増えたようで、異国の水があったのか、ただ適応力があったのか、とにかく大病もせずに無事に帰国してくれたことが一番の喜びです。帰国の途についた彼を空港で出迎えた際、日焼けした顔にいっぱいの笑みをたたえて到着口に現れた彼と1年ぶりに再会した時の気持ちは言葉では言い表すことはできません。
息子の帰国後、我が家で変わったことといえは、今までには全くなかった英語で書かれた手紙や小包が届くようになったこと、そしてアメリカからの国際電話がちょくちょくかかってくることです。そして、いうまでもなく彼自身も大きく変わりました。今までに比べて明るく積極的になったこと、自分から進んで話すようになったこと、自分の考えを人前で述べるようになったこと、Yes・Noをはっきり言えるようになったこと、全くといってなかったボランティア精神に目覚めたこと、他人の気持ちを大切にすること等々。我が息子は「留学」を通してより大きく成長しました。彼自身にとっても素晴らしい経験だったと思いますが、親としても、つくづく留学させてよかったと思います。これも日本青少年育成協会のスタッフの皆様のご助力の賜物であると感謝に絶えません。この経験を活かして、将来の日本を担う一人として、国際社会のなかで大きくはばたいて欲しいと願っています。
|
99年度交換留学生
前川 唯 さん −10ヶ月の交換留学を終えて
兵庫県 長田高校出身(イリノイ州) |
10ヶ月の交換留学を終えて
私は小学5年生の時、父の仕事の関係で1年間アメリカのピッツバーグに滞在しました。それ以来、私はアメリカという国や英語に興味を持つようになりました。そして中学3年生の時、偶然にも日本青少年育成協会主催の交換留学プログラムを知り、「これだ!」と飛びつきました。私がこのプログラムへの参加を決めたのは、アメリカについてもっと知りたい、英語を上達させたいという思いがあったからです。
そして昨年7月下旬、希望に胸を膨らませ日本を出発しました。アメリカで目にした光景は5年前のそれとは大きく違っていました。以前家族と一緒に滞在したピッツバーグには工場がたくさんあり、家のすぐそばにはスーパーやお店がありました。しかし今回留学先に決まった場所は、見渡す限りとうもろこし畑の農業地帯。買い物をするには車で2時間の町まで行かなければなりませんでした。初めてアメリカに滞在した時には家族と一緒でしたから、これといって困ることもありませんでした。しかし今回は日本の家族からも離れ、生まれて初めて自分一人、異国での生活を送ることになり、日本では得られなかっただろう多くの貴重な体験をすることができました。
はじめの数ヶ月は、相手の言っていることや考えていることが分からず、いつも不安な気持ちでいっぱいでした。学校でも不安な気持ちを打ち明けられるような友達がなかなかできず、苦労をしました。しかし、4、5ヶ月経った頃からだんだん英語が聴き取れるようになり、ホストファミリーともその日の出来事を報告し、笑い合えるようになりました。英語の上達と共に学校生活も楽しくなり、友達の数も増えていきました。
私が交換留学生としてアメリカに滞在中に常に心がけていたことは、感謝の気持ちを忘れないこと、そしていつも笑顔で接することの二つでした。異文化の中で生活するということは決して簡単なことではありません。しかし、それはアメリカのホストファミリーの方にとっても同じことです。言葉もろくに通じない外国からやってきた留学生を、10ヶ月もの間、家族の一員として全くの無償で受け入れてくれるのです。相当な努力と我慢が必要なことでしょう。私が異文化に戸惑っていた頃、少しでも早く現地の生活習慣に慣れるよう、ホストファミリーの方は一生懸命助けてくださいました。
私は当初、悩みや困ったことがあっても、あまりホストファミリーに相談せず、いつも自分で解決しようとしていました。そうすることが、自立すること、留学生として一人前だと考えいました。しかし、この10ヶ月で学んだことは、喜びも悲しみも分かち合ってこそ、本当の家族のような関係が築けるのであって、困ったときには人に頼ることも大事なのだということです。自分が心を開いて接してみれば、アメリカには本当に親切で優しく、とても陽気な人が大勢います。私が何かを伝えようとすると、必ず耳を傾けてくれ、何とか理解しようとしてくれました。
交換留学を通して得たものは、私にとっては英語力の上達よりも、人と人とのつながりの大切さを身を持って経験できたことです。私はこの10ヶ月間、本当に多くの人に助けられて留学生活を全うすることができました。たくさんの苦労を乗り越えて得たこの達成感は、大きな自信となりました。これからこの交換留学プログラムに参加される皆さんも、はじめは苦労の連続かと思います。しかし、自分だけではなく他の交換留学生も皆、同じように苦労しています。苦労の先には、その苦労を乗り越えた人だけが味わえる、有意義な留学生活が待っています。このプログラムを通して一人でも多くの日本の高校生が、アメリカで様々な人と出逢い、本当の意味での国際交流を経験できることを願っています。
|
99年度 前川 唯(母)
前川 柳子 さん −留学した我が子を見て |
留学した我が子を見て
昨年7月末に関空から飛び立つ我が娘を見送ってから11ヶ月が経ちました。ようやく自分の手の中に大切な娘が戻ってまいりました。この安堵感!手の届く範囲に我が子がいるということが、どれだけ素晴らしいことかをあらためて実感しました。
「しっかりした娘」ということに絶対の自信を持って留学へと旅立たせた昨夏。その自信がもろくも崩れ去るのに3ヶ月とかかりませんでした。娘曰く、「16年分の苦労をこの 11ヶ月にしてきた」そうで、それも必ずしも誇張でないことは彼女の少し痩せた姿が証明しておりました。
今振り返ってみると、留学当初は本当に胃の痛くなる程心配した数ヶ月でした。周囲の人たちのサポートがあったからこそ乗り越えることができたのだと思います。また、周囲の人たちに支えられつつ、その苦しさや辛さを最後まで頑張りぬいた娘にもよくやったと誉めてあげたいと思います。親元を離れて留学することの成果が、語学習得という当初の目的のみに留まらず、目にみえない娘の成長というかたちで現れたことは、本当に嬉しい限りです。娘自身は、苦しい日々の中からも毎日多くのことを学び、日本に居ては気づかなかったことにも心を開かされたそうです。また、「この貴重な体験を、必ず今後の自分自身の人生に活かせるんだ」と話す娘の姿に、たくましさを感じた次第です。
留学生を送り出した親として、たくさん心配をした1年間でしたが、やはり留学させてよかったと思える今日この頃です。お力添えいただいた日本青少年育成協会のスタッフの皆さん、米国での関係者、ホストファミリー、本当に多くの方々に対し心より御礼申しあげます。ありがとうございました。
|