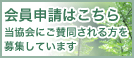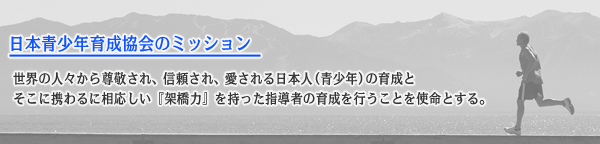変化の時代こそ、不変の理念の追求を
変化が求められる時代
大学入試改革を来年に迎える時期となりました。会員の皆様の現場でも、その対応に激務の日々を送られていることとお察し致します。また、学習ニーズの多様化時代(プログラミング教育・AI導入・英語教育の強化等々)を迎え、その現状に臨機応変な対応をすべく、教育者の意識も、日々問われているように思います。
そして我々が日々向き合っている子どもたちは、我々大人が選択し、創造してきた文化・文明を否が応でも(良い部分も悪い部分も)受け入れ、その土壌を継承していかざるをえない現実があります。彼らが我々と未来を共有し、一緒に創造していく仲間であることは、教育に携わる者として忘れてはいけません。
組織づくり
新年度を迎えるにあたり、組織づくりの在り方について、変化してはいけない部分(ブレてはいけない部分)と、変化を求められる部分、という観点で皆様と共に考えていきたいと思います。
組織を構築し維持運営していくには、【理念】と【経済活動】が車の両輪であることは、私が自社の創業以来意識していることです。どちらが欠けても成り立たない、理念+経済=【経営力】と位置付けております。
我々は社団法人であること、そしてその活動は原則(事務局スタッフ以外は)ボランティアであることを再認識したとき、この組織を運営していくにあたり、重要になってくるのは、【理念】の共有だと思っております。
2018年の活動を振り返って
では、その【理念】の共有という観点で、2018年の活動を振り返ってみます。
- HSK日本実施委員会の活動
まずは「HSK日本実施委員会」の活動ですが、目標であった受験者3万人を超え(34018名)、9年連続での増加を実現しました。これは中国との関係が政治的にいい時代、そうでない時代も変わることなく活動を続けてきた結果です。中国と日本の“かけはし”になって業務に当たろう!を合言葉に、日青協のミッションである【架橋力】を共有して参りました。
活動としては、短期留学、イベントの企画・運営、試験会場の場づくりを実践し、活動の中心になったメンバーは受験者の中から募った方々と、中国からの留学生の皆様です。その結果、2018年は、受験者が日本中国語検定協会の中国語検定を119名上回り、実質日本国内でNO.1の中国語検定ということになりました。
- 指導者育成の活動
またこのHSKの活動を支えているのは、「指導者育成委員会」の教育コーチングです。教育コーチのトレーナー育成の中で、ファシリテーション能力や研修の在り方等を参考に、監督官育成を行ってきました。その結果、我々の想像を超えた活動に発展して、数字に結びついていきました。
昨年、京都大学で行われた指導者育成委員会主催の『アクティブラーニング実践フォーラム2018』では、参加者が過去最高人数(485人)に達し、企画・運営はすべてボランティアで実現できております。
- キャリア教育の活動
また、この影響を受け、「キャリア教育委員会」が長崎の労働局から委託を受けた事業、『若年者の就労支援事業』でも、第4回「NGASAKI仕事みらい博」は、今回初めて学生を巻き込んでのイベントが実現できました。 共に会議を重ねてきた9団体(1.長崎都市経営戦略会議、2.佐世保地域経済活性化推進協議会、3.長崎大学地方創生推進本部、4.長崎労働局、5.ヤングハローワーク長崎、6.ハローワーク佐世保、7.長崎県若年者定着課(長崎県庁)、8.長崎県総合就職支援センター、9.県内大学生ネットワーク)から高い評価をいただきました。この活動も、理念の共有、つまり【架橋力】があってのことです。
ファシリテーターの育成と居場所づくり
私は常々事務局スタッフには「多くの人を巻き込んでください」とだけお願いしております。その中で重要なのはイベントや事業を行う【理念】の確認と共有です。
HSK監督官(中国の留学生と高級取得者<学生・社会人>)の皆様には【架橋力】の理解、教育コーチのトレーナーの皆様には【自立の支援】、長崎の活動での学生の皆様には【主体的な活動の重要性】を共有できたと思います。
そのために、ファシリテーター(=グループによる活動が円滑に行われるよう支援する人、組織が目標を達成するために、問題解決・合意の形成・学習などを支援し促進する人)の育成と居場所(その人の存在を認め、そこに行けばなんとなくやりたくなってしまう場所)づくりを大切にしてきました。共有された理念の下に居場所を求めて集う仲間たちの自発的・主体的行動が、事務局スタッフだけでは成し得ない規模の活動を可能にしたといえます。
組織づくりは居場所づくり、土壌づくり
私が理想とする居場所・空間とは、
なぜかその場所にきてしまう!
声がかかるとなぜかそれを優先する!
例えば、神楽坂を通るとふと立ち寄りたくなる!
うまく言えませんが、決まりをつくって縛るのではなく、内部から湧きあがってくるものを大切にする。お金では得られない“やりがい”に人々が集まり、理念が活動実践に移行していくものだと信じております。理念の共有がもたらすはかりしれない組織力で、我が社団の豊かな土壌を育んでいきたいと考えます。
最後に
企業には企業のバランスがあろうかと思いますが、大きな目でみると社団の運営も同じだと思っております。
変えてはいけないもの、変えなければいけないものをしっかり見極め、次代を生きる子どもたちに何を受け継いでいきたいのか、日青協の活動を通して、ヒントになるものを探していただければと思っております。
|