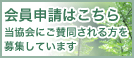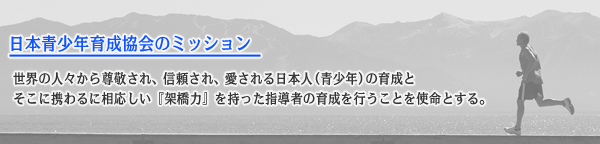世界が「Change」する時代
昨年度は、ここ10数年来金融立国として歩んできたアメリカにおいて、サブプライムローン、リーマンの破綻に端を発し、基幹産業の一角を担う自動車業界におけるビッグ3の危機、著しい景気後退、雇用不安が一気に深刻化した。崖っぷちに追い込まれた感のあるアメリカは、リンカーン生誕から200年を経て、初の黒人大統領バラク・オバマと新政権の方針「Change」にアメリカ危機脱出と再生の夢を託している。
日本においても財団法人日本漢字能力検定協会が全国公募によって決定した2008年度を象徴する漢字(世相を表す漢字)は奇しくも「Change」と同義の「変」が選ばれた。09年3月までに職を失う日本国内の派遣労働者は10万人に達するとも言われているが、圧倒的多数を占める中小企業、小規模事業所の経営環境悪化を考慮すれば、そんな数ではとてもおさまらないほど、国内景気・経営・雇用をとりまく状況は緊迫感を増している。今の状況とは、一言で「危機」ということになるのだろう。漢字というのはよくできたもので、「危機」とは「危険ではあるが(変化の)機会(Chance)でもある」という歴史や先人の教えを、たった2文字の中に示唆している。 「危機」に直面しているのは、アメリカと日本だけではない。これまでの経済システムによる均衡が大きく崩れ、今や百年に1度とも言われる未曾有の世界的経済危機が訪れていると言われている。
そんな中で、世界の主要国は一斉に、環境やエネルギー分野に重点投資する大型景気対策に動き出している。地球温暖化対策という中長期的な課題と目先の景気浮揚策の両方を目指すもので「グリーン・ニューディール政策」といわれるものだ。現時点で投資規模は30兆円を超えるものだ。口火を切ったのはオバマ米大統領。「グリーンジョブ」と題し、今後10年で太陽光や風力発電など再生可能エネルギーに1500億ドルを投じ、400万人の雇用創出を目指す構想を表明している。欧州各国も動き出している。英国政府は2020年までに風力発電を7000基建設し、16万人の雇用を生み出す目標を掲げ、フランス政府も環境分野で50万人の雇用を生み出す計画を作成している。アジアでは韓国政府がいち早く50兆ウォン(約3兆5000億円)規模の「緑のニューディール事業」をまとめている。中国も2010年末までに4兆元(約53兆7000億円)を投じる大型景気対策に環境・エネルギー関連の対策強化を盛り込んでいる。
日本の取り組みはどうかというと、環境省が「日本版グリーン・ニューディール構想(仮称)」の策定に着手。5年後の環境ビジネス市場を少なくとも2006年の4割増にあたる100兆円に育てるという計画で、関連の雇用は6割増の220万人以上を目指して3月をめどに具体策が詰められているところだ。
急速な経営環境悪化に苦しむ日本企業だが、トヨタさえもが世界的な販売不振によって2009年度3月期の連結営業損益は戦後初の赤字に陥る見込みというニュースは衝撃的だった。そのトヨタはいち早く太陽光だけで動く電気自動車開発・実用化へのリーダーシップ発揮を宣言。太陽電池を手掛けるシャープや太陽光発電システムへの新規参入を発表した東芝などの電機メーカー、次世代エネルギーの担い手としての電池メーカーなどが、中長期的な成長期待が株価に反映するなど、知財立国・日本を支える企業主導のグリーン・ニューディールに大いに期待したい。
教育産業人としての「Change」を!
こうした世界や日本の動きの中で我々教育界は、知財立国日本を支え、温暖化防止など「環境分野」をリードする分野に人財を輩出する役割をこれまでにも増して自覚すべきではないだろうか。もとより日本は資源が乏しい国である。知財立国、人財立国になる以外、物心両面を維持していく術などないことを肝に銘じたい。
ましてや「日本のホワイトカラー層ビジネスマンの生産性は先進7カ国中最下位である」「日本企業の従業員は、仕事に対する満足度、労使関係に寄せる信頼感、ワーク・ライフバランスのいずれの項目においても先進23カ国中最下位である(英国FDSインターナショナルによる調査)」「日本人の働く意欲は先進16カ国中15位である(タワーズぺリン社による調査)」などの調査結果については、「自分が源泉」であると考えるとき(教育に携わる者として)これはもう遺憾というほかない。
ただし、現実は想いに反して実に厳しいものがある。昨年まで戦後最長の好景気などと言われていたが、国民の実態は好景気などとは程遠いものであったし、この急速な景気後退は、かつてないほど多くの企業を淘汰するかもしれない。
国税庁の調査によれば、1960年あたりでは中小を含む日本の全企業の7割が黒字であったが、46年後の2006年には黒字企業が33.7%、赤字企業が66.3%と、ほぼ同比率で逆転してしまった。ちなみに創業した会社が5年以内に倒産する確率は約5割、10年以内となると約8割にのぼっており、企業を興すことも維持することもきわめて難しい時代となっている。
こうした厳しい環境は、現在に至るまで23社の上場企業を生み、5万ともいわれる教場数を有する学習塾業界にも共通するものであるし、少なくとも今後2年間は底になると思われる中で、民間教育業界の再編が大きく進む可能性は否定できない。
しかしここで、2009年早々に発表された2つの世論調査結果に注目したい。一つは家計の実態に関する調査であり、一つはゆとり教育見直し後の授業時間数増に関する調査である。
(調査結果1)「暮らし向き」全国世論調査結果(2009年1月3日京都新聞より)
| 問7.あなたは一年前と比べて出費を抑えるなど節約をするようになりましたか。 |
| 非常に節約するようになった |
18.4 |
| ある程度節約するようになった |
61.2 |
| あまり節約していない |
16.5 |
| 全く節約していない |
3.5 |
| 分からない・無回答 |
0.4 |
| 問8.問7で「非常に節約するようになった」「ある程度節約するようになった」と答えた人に聞く)どのような節約をしていますか。二つまでお答えください。(回答者1459人) |
| 食費を節約する |
34.8 |
| 子どもの教育関連費を減らす |
0.3 |
| 衣料品の購入を控える |
36.8 |
| ブランド品など高価な品物の購入を控える |
15.0 |
| 病院に通う回数を減らすなど医療費を抑える |
2.9 |
| 趣味やレジャーの費用を抑える |
36.4 |
| 水道光熱費を抑える |
21.0 |
| 自家用車の使用を控え燃料費を抑える |
14.3 |
| 電話や電子メールなどを控え通信費を抑える |
2.1 |
| 酒やたばこなどの嗜好品を控える |
8.0 |
| 冠婚葬祭費やお歳暮の費用を減らす |
2.5 |
| 電化製品など耐久消費財の買い換えを控える |
17.3 |
| その他 |
0.5 |
| 分からない・無回答 |
0.5 |
- ※調査の方法=層化二段無作為抽出法により、1億人余の有権者の縮図となるように全国250地点から20歳以上の男女3000人を調査対象者に選び、昨年12月6、7の両日、調査員がそれぞれ直接面接して答えてもらった。転居、旅行などで会えなかった人を除き1833人から回答を得た。回収率は61.1%で、回答者の内訳は男性48.0%、女性52.0%。
(調査結果2)全国教育世論調査(2009年1月10日京都新聞より)
前者は、教育費を削るのは最後と言わんばかりの親心が垣間見える調査結果となっており、後者からも教育の現状に対する関心の高さが垣間見える。 いずれも我々が、不況に強い業界であること、国民の注目が高い業界であることを示しており、楽観視する材料とはいかないまでも、こうした世論の信託が教育に携わる我々の「Change」を後押しし、奮起を促してくれていることを忘れてはなるまい。
委員会ごとの「Change」をさらに推進!
本年度は、社団法人日本青少年育成協会(以降略:日青協)の15周年に当たる。そして、運営方針を「委員会組織による機能集団化」に転換して以来、3期目を迎える。
各委員会においては、日青協活動方針に基づいてそれぞれ明確な委員会活動目的を持ち、各正副委員長のリーダーシップのもと年度基本方針を掲げ、最適化された事業を推進することにより、それぞれ初年度を大きく上回る活動成果をあげていただけたと喜んでいる。
たとえばグローバル・エコ・ユース委員会は、より多くの子どもたちが今の地球のこと、将来の地球のことを考えてほしいと願い、ベトナムでのマングローブ植林を実施。今年度は15周年記念行事の一環として、より多くの参加者によるベトナムのマングローブ植林ミッションを実施する予定である。
チャリティー企画委員会も、15周年記念チャリティコンペを実施する予定である。郷ひろみ氏と協力して立ち上げたフォーラム「Love for Our Children Saver's Forum」が実施したフィリピンのストリート・チルドレンを支援するチャリティゴルフコンペは各方面からの多数の協賛を得ることができ大好評であった。本年度も引き続き実施する方向だが、さまざまな理由によって国内に増え続ける恵まれない子どもたちのためのチャリティメッセージに、しっかりと発信していきたい。
会員開発委員会は、会員各位のもつネットワークや「月刊私塾界」等を通じて一定の成果をあげた。しかし公益法人としてのあるべき姿、すなわち「(会員の)会費による運営」の実現にはまだまだほど遠い。本年度は会費の値上げに踏み切るが、会員の大半に影響するような値上げではなく、一部会員に公平な観点から負担増をお願いするものである。また、自動引き落としにさせていただける会員の方々には月会費で徴収させていただくように変更したり、機関紙やホームページでの各会員団体の広報活動への賛助など、会費見直しと同時に負担感の緩和にも配慮したい。新しい試みとしてのフリービブスプロジェクトは広がりを見せており、今後もスポーツ振興を通じた地域貢献と会員開発を推進していく方針だ。
指導者育成委員会および新設されたコーチング認定協議会が中心になって推進する教育コーチング事業は、昨年度コースの名称や料金体系の見直しを実施したため相応の混乱をきたしたものの、継続期間が3年になったり、eラーニングの活用が進んで更新の負担感が軽減するなど、会員のためになることを意図した改革は、認定コーチ数4,030人、認定校数227校まで伸ばしてきており(2009年1月13日現在)、本年度以降のさらなる成果に確実に結びつくはずである。ただ、コーチングレベルと得られる成果(パフォーマンス)との相関関係の定量的調査を急ぐ必要があるなど、今後の発展のために取り組むべき課題も多い。
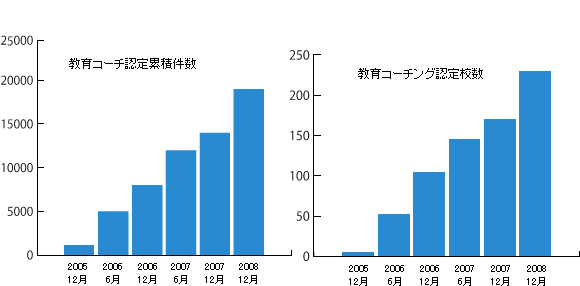
日本人学生の海外留学推進のための国家予算案が12億円増の17億円となったことは、国際交流委員会にとって、これまでの活動の成果や意義が少なからず認められたという意味においても非常にうれしいニュースである。今後積極的に海外への留学生を増やしていくとともに、日本と大きな関係のある中国との交流活性化を視野に入れ、今まで築いてきたHSK中国語能力認定試験の実施基盤をさらに強固なものにしたい。
青少年問題委員会の「地域若者サポートステーション」は一定のニーズをとらえてはいるが、相談会への参加者は減少傾向にあり、「若者自立塾」はよりヘビーな引きこもり増加などによりやや足踏み感がある。ニーズの見直し等、軌道修正の必要を感じている。
会員交流委員会の理事会開催地域の懇親会、新設された業種部会においては、会員とのさまざまな相互提案をして、真に会員のサポートになるような交流企画を推進してほしいと願っている。
広報・渉外委員会では、特に大口の会費を納めていただける会員の方々へのサービス強化を急ぎたい。そして日青協の活動を教育業界や教育に関心を持つ多くの組織・個人に知らしめる様々な広報・渉外活動を通じて、全委員会活動のサポートを徹底してもらいたい。
経営力向上委員会が果たす役割は、昨今の経営環境悪化に鑑みるとき、さらに大きなものと言えるだろう。会員の大多数が教育業界であり、その本業経営の役に立つ(サポートする)斬新な研修や勉強会を、より効果性を重視して実践していきたい。
総務・財務委員会においては、引き続き「新公益法人」への道を模索していくが、より公益性のある社団法人としてのガバナンスや審査基準を満たす理事会ほか会議・行事への出席状況等については、各理事の自覚がより強く求められるところである。2009年度は役員改選の年であり、そういう意味ではワンランク上の自覚でスタートする年度としたいものである。また、会員が増え、委員会を立ち上げて事業領域を広げるにつれ、総務(事務局)の仕事が増えており、専属スタッフ2人体制の限界も感じ始めている。「かけはし」も具体的な活動がよくわかると好評で、本年度も充実した内容でより多くの団体・個人に届くよう活動したい。今後さらにいろいろなことをダイナミックに実行していくためには専従スタッフの充実が必要であり、組織体制の充実をにらみながら、財務については引き続き基本財源の積み立てを継続していきたい。
各委員会の本年度活動方針・事業予定の詳細は、各委員会ごとの平成21年度方針の項に譲るが、各委員会には行事のための行事は極力排して、公益性を意識した上で会員のニーズやウォンツをよりダイレクトに満たすような事業内容の実践に全力を傾ける今年度でありたい。
会員各位の、理念に基づく本業深耕と戦略的「Change」を全力支援!
橋下大阪府知事をはじめ、多くの公教育現場が新しいモバイルメディア(インターネット・通信関連の各種携帯機器)が「学習を阻害する」と結論付け、「携帯電話学校持込の禁止」を宣言し始めている。
禁止政策が数々の弊害を生んできた過去の歴史に学ぶことなく、また徹底的な調査も必要十分な研究もせずに安直に有害性を論じるのはいかがなものだろう。子どもの学習効率を悪化させる側面だけに目を向けるのではなく、いずれ必要となる情報のリテラシーを身につけるために有用な側面、安心安全確保の側面などにも目を向け、なによりユビキタス社会に向かう方向性からはいつでもどこでもだれでもがより快適に学習できるよう、魅力的なコンテンツを開発する努力も一方で必要ではないだろうか。
こうした技術革新への取り組みに限らず、我々は今、ピンチこそ最大のチャンスとして、ピンチをチャンスに変えるために自らを変革することを躊躇するべきではないだろう。また公教育と民間教育を対立軸でとらえる過去のパラダイムとも決別して有機的分業を模索するなど、従来の環境下では生まれなかった新しい発想を持って、これまでしたくともできなかったことへのチャレンジをドンドンやっていける大いなる「機会」が、今なのだ。
そして、日本は理念を大切にする国柄である。理念なき教育や経営、単なる拝金主義、利益至上主義はなじまない。もっとも大切なのは理念であり、その土台の上に立った独自の戦略や戦術を構築せねばならない。
最後に、会員の皆様にあらためて申し上げておきたい。第一に本業を大事にしていただきたい。本業で、この時代を勝ち残っていただきたい。そして日青協の活動を積極的に推進することで、本業に絶大なるプラス効果を生んでいただきたい。社団法人日本青少年育成協会は、そのための有効なバックアップができる公益法人でありたいと願っている。ひるまず、突き進みましょう!!
以上 |