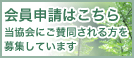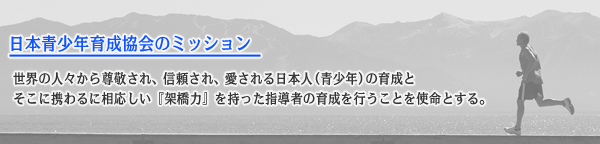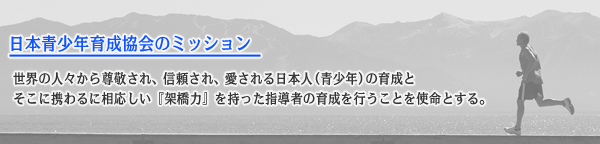学力のさらなる低下と教育格差の拡大
。
経済協力開発機構(OECD)が世界各国の15歳の生徒を対象に行っている学習到達度調査(PISA)の結果、日本の順位が顕著な低下傾向にあることが明らかになった2003年以来、「ゆとり教育で学力が低下した」と盛んに指摘されるようになり、昨年は教育政策の舵が「ゆとり」と決別して大きく切られる大転換の一年となった。
そんな中で 2007年末に発表された同調査(PISA2006)の被験者(当時高校1年生)は小学6年生からゆとり教育(「総合的な学習」のカリキュラム)を受けている世代ゆえその結果が大いに注目を集めていたが、読解力は14位→15位へ、数学的リテラシーは6位→10位へ、科学的リテラシーは2位→6位へとさらに順位を下げただけでなく、同一問題による正答率の比較でも前回を下回る問題の方が多く、理数系の分野を含めた全分野での顕著な学力低下を示す結果となった。この平均値としての地盤沈下同様にはっきりしたことがもう一つある。それは、上位層と下位層との学力格差が前回調査以来さらに進んでおり、上位層すらも学力低下傾向にあることである。
この教育格差は、中央と地方、大企業と中小零細企業、富裕層と非富裕層との経済格差と相関(連鎖)関係があり、教育界の垣根を越えて解決の道を探るべき国家レベルの課題である。地球レベルの二つの課題すなわち南北問題(先進国と発展途上国との経済的格差)と環境問題(地球温暖化、オゾン層破壊、酸性雨、砂漠化等)とともに、大いなる脅威として青少年の未来に立ちはだかっている。
指導者として、日本人として。大人の品格が問われている。
政府は教育基本法の改正を皮切りに、学校教育における三つの再生(学校再生 /地域再生 /教育システム再生)を進めており、とりわけ学校再生における「教師の指導力不足」にはより具体的に改革を行おうとしている。しかしそのてこ入れ策は、一部指導力向上に踏み込んだものがあるものの大半は授業数増や教員数の増加に向けての施策にとどまっており、予算的にも指導力の質的向上にはさほど振り向けられてはいない。
しかし、教育現場で指導にあたる者に批判の矛先をいくら集中させたところで問題は到底解決しそうもない。事態はより深刻である。財団法人日本漢字能力検定協会が全国公募によって決定した 2007年度を象徴する漢字(世相を表す漢字)に、『偽』が選ばれたことに象徴されるように、食品に偽(食肉、野菜、菓子、ファーストフードまで、産地や素材、賞味期限に多くの「偽」)、政治も偽(年金記録、政治活動費、米艦への給油量にも「偽」が発覚し、国会答弁も「偽」)、老舗にも偽(伝統ある土産品にも、名門の老舗料亭にも「偽」)、さらには耐震強度も偽、スポーツ選手、英会話学校にも「偽」…等々。身近な食品から政界、青少年の憧れの対象であるスポーツ選手に至るまで次々と「偽」が 発覚し、もはや指導者に限らず大人が青少年に何を信じたら良いかを示しようがなくなっているのだ。無念ではあるが、子どもたちから「こんな社会に誰がした?」と問われれば、「私たち大人がした」と答えざるを得ない。
「子を観れば親が分かる」と言われる。まさに子どもは大人の「映し鏡」である。やる気、自信、誠実、自立、努力、優しさ、礼節や徳…。鏡に映った子どもに対して、これらすべてに健全であれと願うならば、まずもって大人自らが健全でなくてはならないのは自明である。今まさに、大人のあり方、日本人の品格や倫理観が問われているという認識を持たねばなるまい。
子どもの学力だけでなく、大人の公徳心までがここまで低下している社会だけに、社団法人日本青少年育成協会の使命はますます重大であろう。以下の 4つの柱を平成20年度活動方針として掲げ、決意を込めて取り組んでいきたい。
活動方針1 教育格差是正に貢献し、青少年の生きる力を高め続ける。
冒頭に述べた青少年の学力低下および教育格差拡大は、非常に重大な問題である。社団法人日本青少年育成協会(以下「日青協」と略す)として、いくつかの角度から問題解決を図って行きたいと考える。
厚生労働省のニート対策の実践場全国30数カ所の中で高い就労・就学成果を挙げてきた日青協の若者自立塾沖縄本部(モトブ)の取り組みは、もちろんその一つである。この沖縄自立塾は青少年の自立支援の場であると同時に、日青協認定教育コーチの最高グレード「マスターコーチ」育成の場でもある。より多くの参加者の自立支援を行うべく、一層の発展を期したい。
また、地域教育力向上への支援にも力を入れていきたい。教育格差が進行し、結果として経済的に恵まれない子どもたちが高等教育を受けられなくなるとすれば誠に残念なことである。たとえば沖縄県は、都道府県別学力調査において最下位の自治体であり、経済的格差との相関(連鎖)関係を象徴する最たる地方である。その沖縄県の教育関係者に対して日青協は、京都市、三重県等に続いて 2007年12月、教育コーチング研修の提供を行ったが、今後も継続的な支援を行って行きたいと考える。現在日青協が輩出し続けている本物の指導者とプログラムを持ってすれば、沖縄県が「教育モデル自治体」へと大変貌を遂げることも十分に可能であろう。その成果が教育界全体に大きなインパクトを与え、全国への波及力を持つであろうことを考えれば、日本全国の地域教育力を高める貢献にもつながっていく支援となるはずである。
こうして地方からのアプローチを行う一方、日青協の会員組織を最大限に活かした、全国的な取り組みも必要であろう。
今年度より一定年収(家庭年収 400万円)に満たない合格者に対して授業料全額免除する東京大学の例もあるように、日青協として教育格差と経済的格差の相関(連鎖)関係や企業の社会的責任(CSR)に注目し、経済界とタイアップした「育英基金」の設立(例:子どもたちの教育に携わる教育団体の授業料減免による学力支援+将来人材を受け入れる経済界の育英資金によるタイアップモデル)に向けて調査・研究に着手し、歩を進めていきたい。
一方「ゆとり教育」の象徴的存在であった「総合的学習」が大幅に削減されることによって「気づき」や「主体的な学び」の機会が減少することになるが、この政策転換が間違っても「生きる力」を育てようとする目的に対しての後退につながってはなるまい。今こそ民間企業が教育の本質を提供するチャンスであり、民間の教育力の真価が問われる局面でもあろう。日青協は、民間企業正会員、賛助会員企業、個人会員の皆様と手を携えて、いかんなくその真価を発揮したいと考える。
活動方針2
国際的視野を持った青少年育成を目指して、行動する。
日青協がミッション(使命)の一つに掲げる「世界の人々から尊敬され、信頼され、愛される日本人(青少年)の育成」に関して、欠かすことのできない重要な視点は、「地球温暖化等のグローバルな問題に象徴される視野の広さと、地球規模での行動力を持ったリーダーを育成する」という視点である。
「環境元年」と位置づけられる今年は、とくに地球温暖化に対する危機感が世界的に高まっている。ベトナムにおけるマングローブ植林事業は地球温暖化/ CO2削減問題に対する日青協の取り組みの端緒として「環境後進国」と言われる日本の現状に楔を打ち込む活動であるが、発展途上国における学校建設支援/教育環境整備事業も、地球規模で南北問題を解決して行こうとする日青協の大切な取り組みである。こうした取り組みは、「次代に生きる子どもたちの命と健康」を真剣に考えれば避けて通れない最重要な取り組みとも言えるだけに、一層強力なリーダーシップを発揮していきたいし、何か小さなことからでも確実に行動を起こしていきたいと考える。チャリティイベントもその一環であろう。昨年度は「ニートの自立支援」をテーマに 100万円規模の寄付活動を展開したが、本年度は「南北問題」「地球環境問題」の解決をチャリティ目的として、マスコミへの働きかけやあらゆる告知手段を駆使しつつ、協賛企業や個人の参加の輪を大きく広げていきたいものである。そして、顕著な貢献が認められた団体や個人を顕彰するなどで、さらに大きな運動への発展を図っていきたい。
こうしたグローバルエコ・ユース委員会とチャリティ企画委員会が取り組む領域とは別に、長年の実績を積み上げてきた国際交流委員会による国際交流プログラムは、安易な留学動機の受け入れや日本人同士が群れることを廃し、参加者にとっては他のどの団体のものよりも苛酷で高い自立度を要する本格的なものであり、ボーダーレス社会の中で日本人としてのアイデンティティを持って日本と世界に貢献していけるような青少年の育成を可能にするとの定評を得ている。このアメリカ公立高校交換留学プロブラムや、中国・上海交通大学への短期国際合宿事業も、より多くの人にこれらの活動を知ってもらい、そこへの参加を働きかけていくさらなる努力によって発展させて行きたい。
活動方針3
教育コーチングのさらなる浸透・継続・深化を図る。
冒頭の問題提起において、生徒を指導する立場にある教師の指導力不足が学力低下の主要因の一つとされ、指導力の早急な強化が求められていることに触れた。社団法人日本青少年育成協会では、「架橋力を持った指導者育成」を目的とする主力事業として「教育コーチング」の普及に取り組んできたが、ここにきてますます大きな期待が寄せられるに至っている。
日青協の「教育コーチ検定・教育コーチ養成講座および教育コーチング認定校」事業は、 2007 年 12 月までの 2 年 4 ヶ月で教育関係者を中心に 7,000 名超の認定コーチおよび 180 校超認定校が生み出し、保護者をパパ・ママコーチとして巻き込みながら、「青少年育成のための指導力強化」に成果を上げることができた。日青協個人会員(準上級グレード以上)も一年間でほぼ倍増し、 181 名に達している。また、先に触れた三重県教育委員会、京都市教育委員会、沖縄県教育委員会などの公的機関への導入も大きな成果である。とりわけ京都市教育委員会での取り組みは、約 8,000 名の教師から精査された将来を嘱望されるリーダーたち(校長・教頭候補) 150 名を対象に昨年 4 回にわたって教員研修として実施されたもので、その有用性やめざましい成果は経験豊かな精鋭教師たちから高く評価され、「実施報告書」としてまとめあげられた。このことは、教員免許更新制の導入にともなって教員であり続けるために必要な研修( 30 時間の研修対象の一つ)として位置づけられていく流れや、今後全国各地に設置されて行く予定の教育関連大学院大学の教育プログラムへの採用を後押しする力を持つであろうし、公教育の教育力の底上げにさまざまな形で貢献していく、その大いなる一歩としての意味を持つであろう。
その一方で、公教育に先行して取り組みを始めた民間教育機関に誕生している認定コーチのうち準上級グレード以上のコーチが 200 名以下という現状(およそ 6 人に 5 人は初級レベルに留まっている)からは、民間教育ならではのより高いレベルもしくはより特化した教育サービスを標榜する以上、「教育コーチングを知った」程度のレベルから「成果をあげられる」レベルへと高めて行く緊急性を感じざるを得ない。「更新継続率アップのための仕組みづくり」と併せ、「認定グレードアップの促進」は本年度の大いなる課題である。
活動方針4
委員会活動の充実で、会員増・活性化・満足度アップを。
十分な「機能集団」となり得ていなかった協会組織体質の改善を意図して、昨年度は委員会組織を立ち上げ、各委員会がより「筋肉質」な機能集団づくりを目指して主体的に活動を開始した意義深い年であった。
理事一人ひとりが名誉職的な立場を脱してリーダーシップをとり、機能集団の一員の立場をとることからその第一歩を踏み出した昨年、たとえば会員開発委員会によって正会員数(法人)は 187(2007年12月末)まで伸ばすことができた。この結果には会員開発委員会の働きかけによる紹介や、理事 MLによるスムーズな会員審査のしくみも大いに寄与したと言える。指導者育成委員会(教育コーチング)のがんばりで個人会員も181名に増加した。
なんと言っても会員数は、「会員の会費による運営」を基本とする社団法人にとって生命線である。補助金に依存していた時代を経て、緊急かつ重要であった財政上の課題解決を果たしたことは昨年度のトピックスであった。本年度は、新たな基本財源づくり元年でもあり、来るべき公益法人改革の際の特定法人認定を目指しての財務体質強化と精度アップに取り組む一年でもある。日青協の財政基盤がいよいよ強化の局面に入る一年と位置づけたい。
カウンセリング室(東京)、教育と進路の悩み相談室、サポートステーションの充実とこれらを通じた青少年問題への取り組み、総会/例会/懇親会などでの会員交流の活性化やメルマガ・イベント等を通した会員サービスの充実、会員(=講演者としての登録)による講演事業の推進、会員が保有するコンテンツの有効活用や情報交換、経営力向上のためになる機会提供、新たなパンフレットやセミナー等による会員開発支援や一般企業とのタイアップ推進等、各委員会が担う役割はそれぞれ大きく、委員長・副委員長をはじめとする担当理事各位の強力なリーダーシップと主体的行動を期待してやまない。
一方、 理事会 は開催地の地域会員との交流、一般参加企業との情報交換や交流、コラボレーション開発や会員開発等を意図して北海道、東京、京都、広島、沖縄の各地での年5回開催を行っているが、本年度も各理事がその意図をより明確に持って臨み、事務局においても企画面、運営面、資料内容や情報精度など改善を図りたい。
「絶対積極」を合い言葉に、ビジョンに向かおう。
昨年度にスタートを切った各委員会の活動ぶりは、日青協の組織運営のあり方(事務局を要としたフラットな委員会組織による運営)や理事・会員各々の「あり方」について今後かくあるべしと考えて改革したその方向が、決して間違っていなかったことを確信させてくれた。
その「あり方」とは、「絶対積極」の姿勢・態度である。理事として、委員として、会員としてのあり方だけでなく、会員各位の本業における指導者としてのあり方も然り。世界の人々から尊敬され、信頼され、愛される日本人としてのあり方も然りである。
少子化問題、大学全入時代到来による受験圧力の低下、格差(所得差、学力差のさらなる広がり)の進行など、教育関係者を取り巻く環境は一段と厳しさを増す中で、日青協の多くの会員は教育に携わっている。
指導者である前に大人としての品格さえ問われている今、「絶対積極」の姿勢・態度をもって青少年に対して自ら範を示すことができるか否かは、教育に携わる資質が有るか無いかに等しいと言っても過言ではないだろう。
会員数 1,000(正会員・賛助会員・個人会員計)という数の目標と、活動内容(質)充実という目標の双方を達成し、日本を代表する青少年育成団体となるというビジョンに向かって。
「絶対積極」を合い言葉に、そのビジョンに肉薄する大いなる一年としたいものである。
以上 |