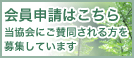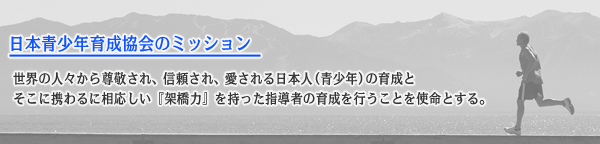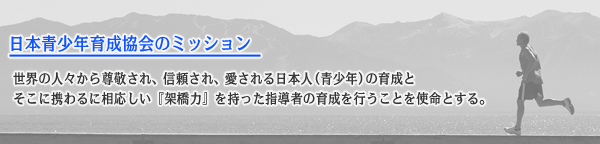教育再生は、今わが国最大の課題である。
「美しい国、日本」をスローガンに、いま政府は教育基本法の改正を最重要課題と位置付けている。
内閣諮問機関である「教育再生会議」が立ち上がり、そこでは学校教育における三つの再生(学校再生 /地域再生 /教育システム再生)についてさまざまな話し合いが進められているが、そうしている間に、皮肉にも「いじめ」による自殺、あるいは親子間・兄弟間の殺戮や虐待が連鎖し、「いじめは卑怯だ、許されないことである」「人を傷つける、命を奪うことは最も許されるべきことではない」ということすら教育できていない現実が、親の責任をほぼ棚上げするかのように激しい非難を受け、「教師の指導力不足」がより厳しく問われている。
学力低下、公徳心低下、自立度低下、生きる力の低下など青少年健全育成が危機的状況にあるいま、「教育再生」というわが国最大の課題に対して、私たち日本青少年育成協会は、まさに正面から向き合うことになる。ついては以下の3つの柱を平成19年度活動方針として掲げて取り組んでいきたい。
活動方針1 教育コーチングの拡大・深化。
世界の人々から尊敬され、信頼され、愛される日本人(青少年)育成のために
健全な青少年の育成を目的として設立され 13年目を迎えようとしている社団法人日本青少年育成協会では、一昨年に会員を対象に実施したアンケートにおいて多くの人たちが「指導者の育成」を要望したことを受け、2005年11月を皮切りに、「架橋力を持った指導者育成」を目的として「教育コーチング」の普及に取り組んできた。
世界の人々から尊敬され、信頼され、愛される日本人(青少年)を育成するという目的に向かって昨年度の最重点事業として推進した「教育コーチ養成および教育コーチング実践校認定事業」は、2007年 11月までの15ヶ月間に民間教育関係者を中心に約3,700名の認定コーチおよび132の認定校を養成し、三重県教育委員会、京都市教育委員会などの公的機関にも導入され、PTA・保護者を巻き込みながら、「青少年育成のための指導力強化」に大きな成果を上げることができた。
また、約 3,700名の認定コーチの中から92人が準上級グレードまで進むことによって、92名の新たな日青協個人正会員が誕生し、正会員(法人)数も146(前年度128)となり、長く歯止めがかからなかった正会員数減少の流れは底を打って上昇カーブを描き始めている。社団法人である以上、最大の懸案であった「会員の会費による運営」に向けて確かに前進し始めたと言えるであろう。
この流れを受けて、本年度においてはさらなる拡大に力を入れるとともに、より重要な方針として「深化(より深く取り組む認定校を増やし、より深く教育コーチングに取り組む上級者を増やすこと)」を掲げたい。
活動方針2 青少年の自立支援・国際人育成への貢献
青少年育成を支援するために
「世界の人々から尊敬され、信頼され、愛される日本人(青少年)の育成」に関して、欠かすことのできない重要な視点は、地球温暖化等のグローバルな問題に象徴される視野の広さと、地球規模での行動力を持ったリーダーを育成するという視点である。日青協では国際交流事業や補助金を得て進めてきたカウンセリング(相談会)事業が、昨年度もその目的に向かって邁進してきた。
カウンセリング(相談会)事業については、いじめ・不登校などの常態化を背景に、医療行為を必要とする学習障害に対する日青協事業の限界もあって減少傾向にあったが、支部事業として開始した日青協沖縄自立塾は、沖縄支部関係者のご努力とコーチングを採り入れた独自のプログラムで全国20数カ所の若者自立塾の中で最も高い就労・就学成果を挙げ、「ニート問題」に一石を投じることができた。
また、国際交流事業は、過去日本人留学生が海外で事件に巻き込まれる等で一般的には下火になりつつあったが、日青協のそれは、安易な留学動機の受け入れや日本人同士が群れることを廃し、参加者にとっては他のどの団体のものよりも苛酷で高い自立度を要する本格的なプログラムとして、ボーダーレス社会の中で日本人としてのアイデンティティを持って日本と世界に貢献していけるような青少年の育成を可能にするとの定評を得ている。そしてアメリカだけでなく、中国やベトナムを舞台にした、青少年の国際交流舞台の拡大も進行中である。それだけに、本年度もそのことをより多くの人に知ってもらい、そこへの参加を働きかけていくことが大切である。
活動方針3 協会組織の機能集団化
筋肉質で活動力あふれる会員組織(機能集団)を目指して
先に「会員の会費による運営」を基本とする社団法人にとって最大の危機であった会員数減少が底を打って増加に転じたことに触れた。この面からは、長らく財政上の課題解決が緊急かつ重要であった日本青少年育成協会の財政基盤整備への着手ができた一年であったと言えるだろう。今後、会員数を今の 10倍にするという長期的な目標を掲げるが、たとえ数の目標を達成したとしても活動内容(質)をともなわなければ、日本を代表する青少年育成団体とはなり得ない。
その目標と照らしたとき明確になる課題は、「機能集団」となり得ていない現在の協会組織体質の改善であろう。具体的に言えば、同じ正会員でも、日青協の活動への参加度合いはまちまちで、単に会費を払っているだけに終わっている会員も少なくないという実情をどうするのかと言い換えてもいい。
活動に参加する正会員が限られている(すなわち会員の活動状況が活発ではない)のは、もちろん魅力的な活動(活躍の場)を提供できていない協会(理事会)の問題であるという考え方もあるだろう。
しかし、もとより青少年のために活動するのが正会員と定義されている以上、それを会員のあるべき姿とする方針を掲げ、その同意を形成した上で活動度合いの著しく低い正会員には退会勧告も辞さずの(逆に活動に寄与する正会員はさまざまな形で報いる)姿勢を持ち、より「筋肉質」な機能集団づくりを目指していくべきであると考える。また、この現状を打破するには、理事一人ひとりが名誉職的な立場を脱してリーダーシップをとり、機能集団の一員の立場をとることからその第一歩が始まるであろうと考える。
「厳冬の時代」なればこそ。
少子化問題、 2007年問題(大学全入時代到来による受験圧力の低下)、格差社会(所得差、学力差のさらなる広がり)など、教育関係者を取り巻く環境は一段と厳しさを増している。
多くの会員が民間教育に携わっていることを考えれば、まさに「厳冬の時代」が到来した感は否めない。今まで以上に「本業」に邁進しなければという危機感は会員に共通する思いであろう。
そのことを十分に踏まえて、日青協の活動への参加が「負担」になるだけではなく、日青協の活動を通して本業に(「負担」を超えるだけの)寄与をするものとなるよう、互いに知恵を絞り、限られた時間を有効に使って、
「世界の人々から尊敬され、信頼され、愛される日本人(青少年)の育成と、そこに携わるに相応しい『架橋力』を持った指導者の育成を行う」
という協会ミッションの実践に務めたいものである。
以上 |