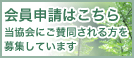■5月6日、早朝の集合時刻に眠い目をこすりながら、続々とキャンプリーダー候補たちが、神楽坂のオフィスに集まってきた。今回のプレキャンプは、夏に子どもたちを集めて実施する「森と農業キャンプ」のキャンプリーダーとなるボランティアの若者たちの、現地研修という位置づけになる。集まった若者は東京11名、大阪2名の計13名。男女比率は圧倒的に女性が多く、男性は1名のみの参加となった。これに事務局サイドのおじさんたちが関東から3名、関西から3名加わり、19人の参加者によるプレキャンプが始まった。レンタカー等も繰り出し、朝の高速を使いながら現地に到着したのは午後1時頃。今回のキャンプの舞台になるのは長野県大町市、白馬山麓にある「森とくらしの郷」という、広大な面積の、文字通り”山”という表現が似つかわしい、水も電気も通っていない場所である。山のそばには高瀬川を抱き、野生のカモシカや日本猿、タヌキなどと同居する自然とのふれあいに溢れている。到着後、宿泊場所となる山小屋に荷物を置き、山の管理者であり、このキャンプのアドバイザーでもある「武蔵林業社」の朝重氏と八木氏からレクチャーを受ける。若者たちは、事前説明会で聞いて想像していたよりも、さらにネイチャーな現地を見て、少し驚いているようだ。「森と農業のキャンプ」の目玉は、この広大な森の中で暮らすということと、もうひとつ、子どもたちが自分で農作物を収穫する、という農業のカリキュラムのふたつから構成されている。農地は山から少し離れた大町温泉郷に程近い200坪の畑を、当地の地主さんからお借りすることができた。
■早速、参加者が農地に行って、本番キャンプで収穫するための作付けをする農作業班と、炊事班とに分かれて作業を始める。慣れない手つきで農具を持ち、まずはウネづくり。今回作付けしたのは、夏に収穫ができるナス・キュウリ・カボチャ・トウモロコシ・ピーマン・オクラと大豆・蕎麦である。農作業の指導は、関西から参加された在田氏と、武蔵林業社の八木氏が担当してくださった。一日目は夕方6時半までひたすらウネづくりに専念した。自分たちが始めて作った畑を、充実した眼差しで見つめている、若者たちの表情が印象的だった。そして農作業で疲れた体を癒すために大町温泉に。暮れなずむ山の稜線を見ながら入る露天風呂は最高だった。山に戻ると、炊事班の用意してくれた特製”鳥鍋”が待っていた。ふだん都会では使わない石油ランプの火影で、参加メンバーの自己紹介。生気溢れる若者たちと、楽しく語り合いながら、星空のもとで食べる食事はこのうえもなくウマイ。一日の程よい疲れが出てきて、ひとりまたひとりとシュラフに潜り込んでいく。
■美しい野鳥の声で、二日目のプログラムが始まる。午前中は山歩きだ。高瀬川のほとりまで、約30分のウォーキング。本番のキャンプの時に子どもたちを楽しませるためのスポットを見つけたり、川辺で休憩したり、バードウォッチングを試みたり・・・。朝食を食べながら、ミーティング。このキャンプに参加した、それぞれの思いを語り、しっかりとした個々の考え方に互いに共感し合う。二日目午後は念願の作付け。苗や種を蒔き、ウネにマルチと呼ばれる黒いビニールをかぶせ、農業用水から水をひくと、立派な畑の完成。一日目より、さらに大きな充実感があった。農業のプログラムが終了すると、そこここで「よく出来たね」「ここまで出来るとは」といった声があがった。山に戻り最後のミーティング。来た時とは変わり、「森と農業のキャンプ」を成功に導く主人公としての自覚を持った、若者たちの顔がそこにあった。夕方4時、山に別れを告げ、関東・関西への帰路につく。午後11時、たいした渋滞もなく、神楽坂に着き解散。少し疲れた体と二日間の貴重な体験をみやげにキャンプリーダーたちが帰っていった。 |